事業存続に関わる“炭素予算”とは?
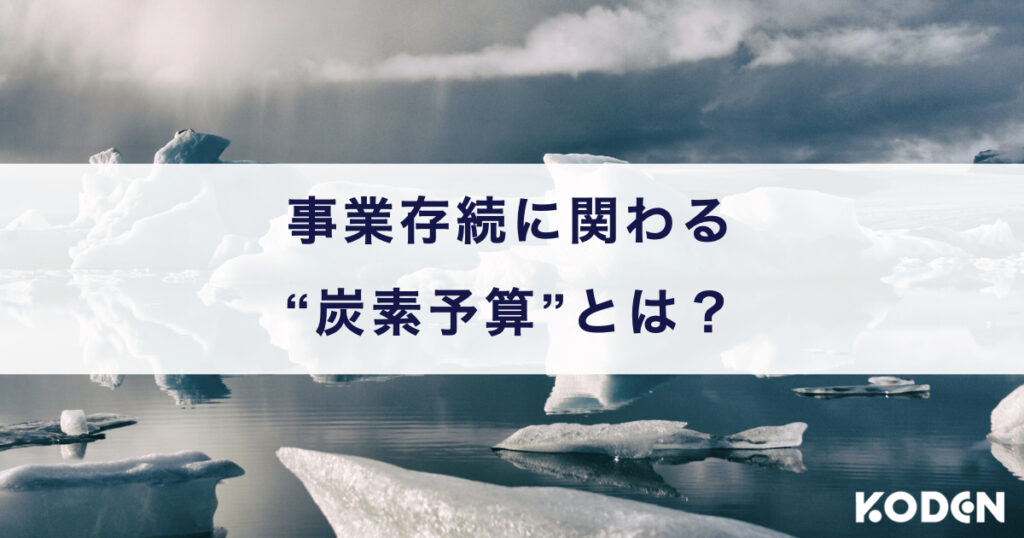
前回の記事では、なぜ今「脱炭素」に注目が集まるのか、私たちが直面する最悪な4つのリスクについて解説してきました。
では、これらのリスクを回避するために何が必要なのか、実際に求められる変化の規模とスピード感について説明していきたいと思います。
この規模感と時間軸の理解度は、企業としての成長に直結する分野です。既に世界の投資家たちは、企業が気候変動に対して取り組めているか否かを、投資を決める上での重要な指標の一つとして捉えています。
求められる”気温上昇1.5℃以内”
最新の科学的知見を取りまとめるIPCC(気候変動に関する政府間パネル)によると、このまま気温上昇が進行すると、地球は今後、ある時点で取り返しのつかない危機的な状況に陥るとされています。
その「ある時点」を迎える前に、気候変動を食い止めようと国際社会が合意したのが「パリ協定」です。
パリ協定(2015年)
「世界的な平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追及する。」
2℃の削減目標を掲げた「パリ協定」ですが、その後の2018年には、上昇を抑えるのが2℃の場合と1.5℃の場合で、どのくらいの影響の差があるのかを示した「1.5 °C特別報告書」が発表されました。現在では1.5℃に気温上昇を抑制することがスタンダードになっています。
ここで、明確にしておかなければいけないことが、IPCCはあくまでも客観的に、科学的知見を取りまとめていることです。地域によっては、気温の上昇によって恩恵を受ける人たちもいるかもしれません。また、経済学者であれば、費用便益の視点から目標を定めるべきと語るでしょう。
IPCCの報告は「気温上昇を何度に抑えるべき」という価値判断を伴う見解ではなく、1990年に比べて2〜3℃以上気温が上昇した場合、全世界的に対策コストより損失のほうが大きくなる可能性が非常に高いとしているのです。
さらに、気温上昇がある臨界点を超えると、様々な自然の連鎖反応が生じ、不可逆的に気温上昇が進んでしまうリスクも存在しています。例えば、永久凍土の融解により、CO2よりも強い温室効果を持つメタンが地表に姿を現し、気温が上昇する「自然のフィードバック」が想定されます。
たとえ人間社会が温室効果ガスの排出をゼロにしたとしても、自然の作用によって気温が4〜5℃上昇してしまう可能性があるのです。
それを防ぐためにも、今私たちは急ぎ、気温上昇の抑制に取り組まなければいけません。
炭素予算(カーボンバジェット)
それでは、どうすれば気温の上昇を1.5℃以下に抑えることができるのでしょうか。それを考える上で、重要になってくるのが「炭素予算(カーボンバジェット)」の概念です。
前提として、気温の上昇は、人間が過去から現在にかけて排出した(そして今後排出される)CO2の累積量に比例します。
ここで重要なのが「累積」という部分です。
CO2などの温室効果ガスは、一度排出されると長い期間大気中に留まります。産業革命以降、世界各国はCO2を排出してきたため、1.5℃目標の達成のためには、この溜まっている分を考慮したうえで上限を課さなければなりません。この上限が「炭素予算」と呼ばれます。
そして、きちんと理解しておかなければいけないことは、人間社会は既に大量のCO2を排出しており、残された炭素予算は僅かであるということです。
IPCCによると、2017年までに排出されたCO2の累積量は約2200Gtであり、それが既に引き起こされた1℃の気温上昇の原因となっています。では、気温上昇を1.5℃に抑えるための累積排出の上限はというと、約2600Gtで、許された残りの排出量は400Gtあまりとなります。
参照:Global carbon budget bucket 2020
最近の世界の年間CO2排出量は40Gtあまりで、このままではあと10年で予算を使い切ってしまいます。
国連が2030年の10年を「Desicive Decade(決定的な10年)」としている理由はここにあり、炭素予算は気候危機を回避するための最重要KPIなのです。
炭素予算の概念が市場に及ぼす影響
先述のとおり、現代を生きる私たちが取り組まなければいけないのは、残された炭素予算を出来るだけ効率的、効果的に使い、それを使い果たす前にCO2を出さない社会に転換することです。
毎年の排出量を減らすことができれば、予算を使い果たすまでの期間も伸びるので、その分CO2排出量0の社会へ移行していく猶予が発生します。
そのようにして時間を稼ぎつつ、2050年までの約30年間で世界全体での排出ゼロを目指していく「2050年カーボンニュートラル」の考え方が広まっています。
では「どこから(何から)先に減らしていくか」言い換えるならば「どこに炭素予算を優先的に配分するか」が、次に私たちが直面する問題です。
これには物事の「価値や必需性」また「代替手段の有無」を基本軸として様々な活動を評価し、優先順位を考える必要があります。
例として石炭火力発電を考えてみましょう。
業種ごとの総資本営業利益率と炭素排出量の関係により、炭素生産性(CO2排出1t当たりの経済的な付加価値)を数値化することができます。
石炭・石油業界の炭素生産性が全業種の中で最も低い事実は想像に難くありません。
先述の2つの軸で考えてみると、付加価値の高い製品やサービスを作るためにも電力などのエネルギーは必要ですが、そうでないものも多く存在しているでしょう。また、電力には既に再生可能エネルギーという別の生産方法があり、多くの分野でその代替は可能です。
さらに「できる範囲で」や「やれるところから」という考えではなく、炭素予算から導かれる規模・スピードで脱炭素を進める必要であるという認識が広まってきています。また、各国の中央銀行や投資家たちが、リスクの高い石炭関連資産から投資を引き揚げる(ダイベストメント)も加速しています。
実際、全世界の化石燃料資産のうち、約8割が不良在庫化するという試算もあり、炭素予算を考えずに資産の値付けが行われている「カーボンバブル」がはじけた場合の金融システム全体への影響は計り知れません。
このように、炭素予算を起点に考えることで、脱炭素社会への転換期に伸びていく事業、縮小していく事業が、炭素予算から見えてきます。
「炭素予算をベースに物事を考える」視点は、自社の生存戦略としても今後は必要不可欠なのです。
参考文献:松尾雄介「脱炭素経営入門 気候変動時代の競争力」
記事を書いた人

