太陽光発電の「Engineering(設計)」とは何なのか?
A. 発電・自家消費シミュレーション、設備・電気設計、最適提案、そして関係各所への許認可申請までを一貫して遂行するプロセス全体を指します。
図面作成にとどまらず、実発電の再現性と法令適合、導入までの段取りを設計品質として担保することが本質です。
要約
太陽光発電システム導入における「設計」の役割:
太陽光発電における「Engineering(設計)」とは、単なる図面作成に留まらず、発電量や自家消費量のシミュレーション、設備や電気の設計、条件に応じた提案、さらには電力会社や自治体への許認可申請対応まで含む一連のプロセス全体を指します。これらを一貫して担うことで、初めて「良い設計」が成立します。
「設計」における恒電社の強み:
恒電社は、日射量データを用いたシミュレーションにおいて、実績値を下回らないよう控えめな数値を提示し続けています。他社との比較では不利になる可能性もありますが、顧客に誤解や失望を与えないことを重視しています。これは「地域で逃げも隠れもせず、正々堂々と仕事をする」という企業文化と信念に基づいた姿勢です。
許認可対応と申請ノウハウ:
太陽光発電導入には経産省や電力会社など多岐にわたる申請が必要で、単に書類を出すだけでなく、タイミングや流れを熟知したノウハウが不可欠です。恒電社では「申請プロセス表」を活用し、事前に必要書類や押印を一括で用意する仕組みを構築。これにより顧客の負担を減らし、スムーズな導入を実現しています。
解説者
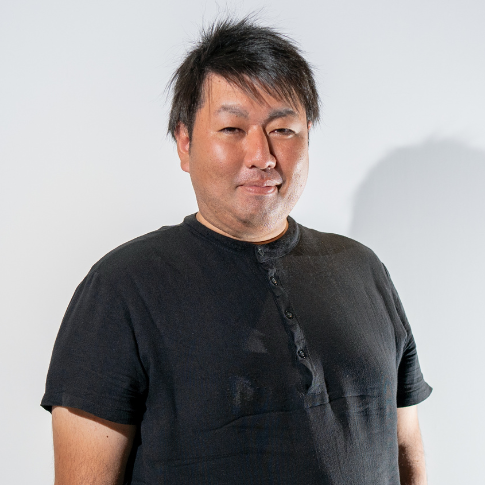
インタビュアー

EPCの「Engineering(設計)」とは?
━━━太陽光発電設備工事における「Engineering(設計)」は具体的に何を指すのでしょうか?
シミュレーション設計からご提案、申請までです。
その上で「良い設計ができます」と言い切るためには、単なる図面作成だけではなく、以下のような一連の業務を一貫して対応できることが求められます。
- シミュレーションの実施:発電量や自家消費量のシミュレーション
- 設計能力:太陽光発電設備や電気設備の設計
- 提案力:上記シミュレーションや設計内容をもとに、お客様ごとの条件に応じた最適な提案
- 許認可対応:設計内容に基づいた申請対応
- 電力会社への届け出
- 市区町村の役所への申請手続きなど
これらを一貫して対応できてはじめて、「良いエンジニアリング=設計ができる」と言える状態です。
恒電社が重視していること
━━━シミュレーションに関して、恒電社では何を重要視されていますか?
恒電社では、お客様の拠点における過去1年分の実際の日射量データベースを活用して発電量のシミュレーションを行っています。また、過去40年分の平均日射量をもとにしたシミュレーションも併用しています。
これにより、実際の発電量がお客様にお伝えした想定の数値を下回ったケースは、現時点では一切ありません。
━━━そもそも、シミュレーションは難しいものなのでしょうか?
難易度の前に、シミュレーションの正確性・確度に対する考え方が、EPC事業者によって異なるのではないでしょうか。
たとえば、シミュレーション上は本来「100」発電するという結果が出ていても、それをそのまま「100発電します」とお客様に伝えてしまうと、もし、少しでも下回ったときに「話が違う」となってしまいます。
そこで、恒電社ではあえて「80」程度と控えめに提示します。
ただしこのやり方は、他社とシミュレーション結果を比較された際、数字が低く見えるため、恒電社にとっては決して有利とは言えません。
それでも、あえてこの姿勢を貫いています。
━━━なぜ、そこまでして慎重な姿勢を取るのですか?
お客様を裏切りたくないからです。それが恒電社にとって「当たり前」です。
仮にシミュレーションを上回る結果が出た場合には、それだけお客様に喜んでもらえますしね。
私たちは、埼玉県に拠点を構え、地域のお客様と直接仕事をしてきました。売ったら終わりではなく、継続的にお互いが支え合い、発展するためにも、正々堂々と対応すべきです。
これは代表の恒石の考えが反映されていると思います。「私たちは埼玉で、逃げも隠れもしません。正々堂々と仕事をさせていただきます」という信念が企業文化として根付いています。
ただ、そもそも、太陽光発電のシミュレーション精度は高いです。その理由は、地球の気候がそこまで大きく変わらないためです。
今年は雨が多いなと感じることがあっても、年間を通して見ると日射量には大きな変動がありません。そして、そのわずかな変動も「安全率」が吸収してくれます。
そのため、恒電社が提示するシミュレーション値を実際に下回ることは、基本的にはありません。
使っている元のデータはどの企業も同じであり、使用する数式も共通です。それでも、導き出される結果には大きな違いが生まれます。
「許認可対応」について
━━━「シミュレーションの実施」「設計能力」「提案力」は「Engineering(設計)」の文脈から理解できました。4点目の「許認可対応」も「Engineering(設計)」の力量が問われるのでしょうか?
許認可の申請には一定のノウハウが必要です。例えば、ソーラーカーポートを設置する場合、建築確認申請の届出が必要となります。そして、その申請書の「出し方」にもテクニックが存在します。
━━━建築確認申請以外に、どのような申請がありますか?
他にも、売電を伴う発電設備であれば、固定価格買取制度(FIT)の認定を取得するために、経済産業省への申請が必要になります。
自家消費型太陽光発電では、電力会社への申請が必要です。実際には、皆さんが想像する以上に複雑な申請プロセスが多く存在します。
━━━申請書の作成に、テクニックが必要なのでしょうか?昨今の生成AIなどで代替できないのでしょうか?
生成AIでも、申請書の作成自体は不可能ではありません。
ただ、申請は一回出して終わりではありません。たとえば東京電力と経済産業省に申請する場合、それぞれに異なる提出タイミングや対応部署があり、バトンを渡すように順次処理を進めていく必要があります。
この流れを把握していないと、処理に非常に時間がかかってしまいます。
━━━申請ノウハウというのは、具体的にどういったものですか?
弊社には「申請プロセス表」があります。
例えば、ある設備の申請をする場合には「これとこれとこれが必要だ」という一覧があります。そして、そのプロセスの中で、お客様の捺印が必要となるタイミングも事前に把握しています。
そのため、都度お願いするのではなく、最初にまとめて必要書類を提示して「すべてに一括で捺印をもらっておく」といった工夫をしています。
詳しくは、「申請プロセス表」を作成した弊社の経営企画室 カスタマーサポートチームの向井さんに聞いてみてください。
関連記事を読む
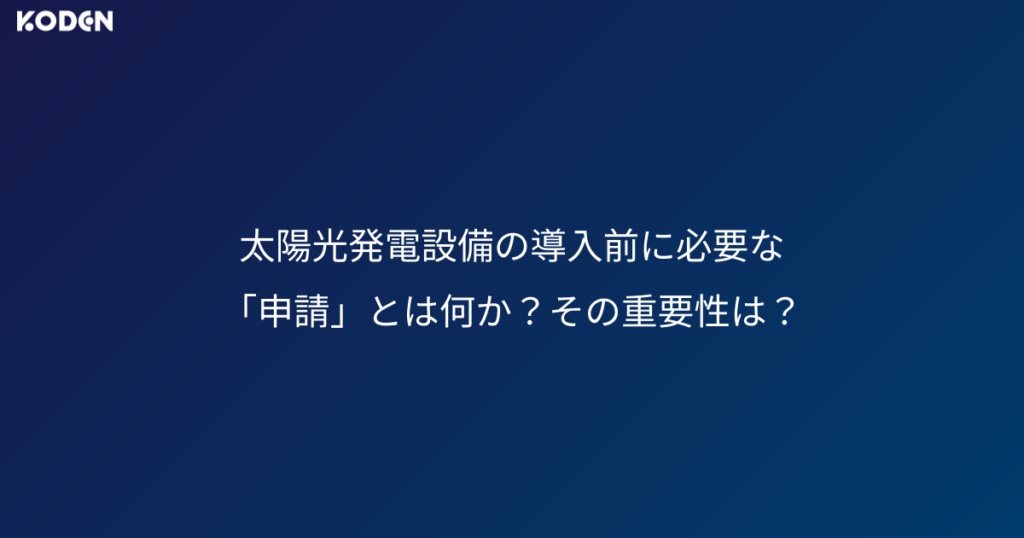
━━━普通であれば申請の途中で「この書類に印鑑をもらってください」となるところを、先に印鑑を集めておいて、後から「もうあります」と即座に対応できるわけですね。
そうです。企業様によっては、書類にご捺印を頂く際に社内稟議を必要とするケースも少なくありません。事前に必要書類をすべて洗い出してお渡しすることで、お客様がストレスなく太陽光発電設備を導入できます。
━━━なぜ、そのようなノウハウがあるのでしょうか?
まず第一に、恒電社は以前から売電の太陽光発電設備を多数手がけてきた実績があるためです。また、電気工事の中でも電力会社との申請や協議のやりとりを長年してきた背景にあります。
さらに、カスタマーサポート担当者のスキルも大きいです。CSは過去にやったことのない申請でも、周囲に情報を集めながらゼロから形にしていく力を持っています。
━━━国がそういった申請マニュアルを出していないのですか?
出していますが、ざっくりしたものです。たとえば、経済産業省が出しているマニュアルでは、全国の電力会社に共通する内容が記載されています。
しかし実際には、電力会社によって同じ申請でも名称が微妙に異なります。そういった違いも含めて、私たちはテクニックの一部と考えています。こちらも詳しくは向井さんのお話をご参考ください。
記事を書いた人

